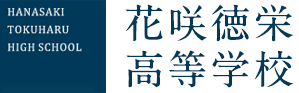令和7年8月2日(土)、食育実践科2年生中島千遥さんと出村優衣さんの2名が第14回ご当地!
絶品うまいもん甲子園関東甲信越エリア選抜大会に出場しました。(選抜大会への出場は2年ぶり4度目)
地元加須市の名物うどんと川越のさつまいもを使用した「さつまん」を考案。老若男女世代を問わずに食べられて、中食としての利用を見込んだパッケージに仕上げました。大会当日は調理、審査員による試食、プレゼン審査と最終PR、質疑応答が行われました。出場した二人は、緊張しながらも練習の成果を遺憾なく発揮し、試食した審査員からも「とても美味しい。明日にでも販売できるクオリティである」など高評価をいただき、確かな手応えと達成感を得る貴重な経験となりました。
結果は惜しくも全国大会には届きませんでしたが、9月12日(金)~15日(月)に実施されるSNS(LINE)による応援投票で最多得票数を獲得すると敗者復活で全国大会への出場ができます。
ひとりでも多くの方々にお声がけいただき花咲徳栄高校「さつまん」に投票をお願いします。
(詳細は、ご当地!絶品うまいもん甲子園HPをご確認ください。)
令和7年7月21日(月・祝)〜30日(水)、食育実践科2、3年生の希望者を対象に17カ所でインターンシップを実施しました。約1週間、就職希望の生徒や調理師免許の取得を目指すために現場での実践的な経験を積みたい生徒が、参加しました。
インターンシップを終えた生徒は、知識や技術だけでなく、飲食業界で働くことの素晴らしさや大変さを実感したと感想を述べており、自身を成長させられた実りあるものにすることができました。インターンシップを実施した企業には、卒業生が働いている所もあり、生徒は、とても心強かったようです。
ご協力いただきました各企業の皆さまには、大変感謝しております。
実習先(五十音順)
※赤坂四川飯店
※(株)アルピーノ
※イタリア食堂テラマーテル
※ホテルオークラ東京
※小山グラウンドホテル
※(株)カーディナル
※加賀屋 銀座
※くら馬
※コロンバン
※芝パークホテル
※清水園
※築地すし好
※つばめグリル
※東晶大飯店
※東天紅
※パレスホテル大宮
※ホテルブリランテ武蔵野
令和7年7月4日(金)、幸手中学校で出張授業を実施しました。
中学3年生を対象にフルーツの飾り切りの調理実習を行いました。
本校食育実践科3年生9名が、各班で手伝い生徒として中学生の実習を補助させていただきました。
令和7年6月27日(金)、食育実践科3年生は、日本調理技術専門学校(Nitcho)様にお越しいただき、洋食の外部講師実習を行いました。今回は、ポークカレーとサラダをご指導いただきました。生徒にとってなじみのあるメニューは、これまでの経験から味や見た目の比較ができたり、美味しくするための工夫を考えたりすることができる実習でした。
令和7年7月19日(土)、本校にて龍興寺(加須市)「こども寺子屋」が開催されました。
小学生1年生から6年生の合計64名が低・中・高学年に分かれ、調理実習を行いました。サラダラーメン、焼売、フルーツ白玉を食育実践科1、2年の生徒が先生となり小学生に優しく教えました。食育実践科の生徒は、充実した時間となるよう日頃の実習で培った対応力を発揮しました。
試食の際には、合掌して「食事の五つの誓い」を大きな声で唱え、和やかな食事の時間を過ごしました。高校生にとっても貴重な経験となり大切なことに改めて気づくことができた1日となりました。